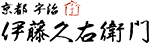Kyoto tsu
京都通
- 2009/2/14
第113回 神泉苑『恋をはじめたいとき、訪れたくなる京の史跡』
風情溢れる庭園は宮廷の遊び場やったんどす
二条城といえば京都の定番観光スポットの一つですが、その二条城に大通りをはさんですぐ南側にある「神泉苑」はあまり知られていないのではないでしょうか。
神泉苑が生まれたのは、都が平安京に遷移されるとき。
桓武天皇が平安京とともに禁苑(一般の人が入れない、皇室のための庭園)として造営したのが由来で、平安京最古の史跡とされています。

もともと京都盆地は湖の底で、それが次第に干上がったことで今の姿になったという説がありますが、神泉苑にはかつてその地が湖の底だった名残があり、豊かな清流が湧き出すことから「神泉苑」と名づけられたそうです。
そんな自然そのものの姿を活かすようにして造られた美しい庭園です。
そして、かつては今よりも大きな庭園でした。
現在では二条城が二条通りを分断するように建っていますが、平安時代には二条城がまだ存在しておらず、北は二条通りから南は三条通りまで、東は大宮通りから西は壬生通りまで広がる南北4町東西2町という広大な庭園でした。
平安時代の神泉苑は、桓武天皇の時代から歴代の天皇が、舟遊びや観花、詩歌、管弦、弓射、相撲といった行事が行われた華やかな宮廷の遊び場でした。
現在の私たちにも馴染み深い「花見」も、嵯峨天皇が行った桜を楽しむための宴会が始まりだといわれています。
今では時代の変化とともに当時の8分の1ほどのサイズになりましたが、大きな池を中心に季節の花々や美しい緑に包まれ、風情溢れる庭園であることに変わりありません。
しかも、他の有名な京都の観光スポットとは違い、比較的人が少ないのでのんびりと散策できるのも魅力です。
願い事は一つしかあきまへんえ
神泉苑にはもう一つ重要な顔があります。
それは、京都が干ばつや疫病に見舞われたとき、雨乞いや疫病を治めるための神事が行われる場所だったということです。
ここで雨乞い祈祷などが行われて雨が降ることで、天皇の神聖化を高めようとしたとも考えられています。
まさに王権の象徴のような存在だったのですね。
なかでも有名なのが天長元年(824年)に起こった日照りに対する大規模な雨乞いです。
東寺の弘法大使空海が呼ばれ、現在も神泉苑に架かる赤い橋「法成橋」で雨乞い祈祷を行ったのです。
そのとき空海は北インドの無熱池(現在のチベットのマナサロワール湖であると考えられている)に住むといわれた善女龍王をお呼びになり、空海の法力が叶って全国に雨が降ったのだとか。
それ以来、善女龍王は神泉苑にお住みになったと考えられ、龍神様が住む場所として、祈雨が盛んに行われるようになったのです。
神泉苑には、その善女龍王を祀る社があります。

そしていつからか、祈祷が行われた法成橋を一つだけ大切な願い事をしながら渡ると願いが叶うといわれるようになりました。
「一つだけ」というのがポイントのようなので、訪れる前にぜひ熟考されるのがおすすめです。
あれは修学旅行生でしょうか、2名の女子高生が真剣な面持ちで一人ずつ橋を渡っていたのが印象的でした。
また、神泉苑は祇園祭の起源の地でもあります。
祇園祭は京都で蔓延した疫病を治めるために始まったというのは有名な話ですが、その源流となったのが神泉苑で行われた御霊会です。
平安時代の京都の人々は、疫病が流行るのは恨みを残して死んだ人の御霊の祟りであると考えられていました。
そのため貞観11年(869年)、鉾を当時の全国の数である66本を作り、神泉苑に集まって行列する御霊会が行われたのです。
これが後の八坂神社の祭りとなっている祇園祭へと続いていったのです。
雨は恋のはじまりどす
平安時代の終わりごろ、神泉苑は王権勢力の落ち込みとともに荒廃していったようです。
しかし、まだ重要な場所と位置づけられていたようで、後白河天皇の時代の建久2年(1191年)にも、雨乞いが行われています。
ただ、かつてのように祈祷僧を呼んで雨乞いをするのではなく、舞姫100人を集めて舞を舞って龍神を喜ばせようと後白河天皇は考えたのです。
芸能好きといわれた後白河天皇らしい発想ですね。
そのとき、検非違使の判官として後白河天皇のお供をしていたのが源義経です。
舞姫99人が舞を舞っても雨が降らなかったのが、100人目の舞姫が舞うと突然雨が降り出したのだとか。
その最後の舞姫が舞の名人と呼ばれた静御前です。
これが義経と静御前との初めての出会いであると『義経記』では記されています。
雨にまつわる出会いというのは、いつの時代においてもロマンチックですね。

これにより縁結びの神様がいらっしゃると信仰され、苑内には恋みくじもあります。
観光客が比較的少ない中でも、神泉苑を一度訪れた女性は、たちまち心を引きつけられるというのも納得してしまいます。
また、神社と寺の両方が苑内にあるため、神前式や仏前式などの婚礼の儀式も行われています。
強い絆を結びたいという男女の思いを叶えてくれそうです。
そのほか節に応じて由緒ある催しものがあるのも見所です。

最初の催事は、歳徳神の恵方回しです。
神泉苑には日本唯一の歳徳神が祀られているのですが、これはこの年の幸運の方角である恵方を向くように方向を変えられます。
それがまさに年の変わり目に行われるのです。
そんな催事のなかでも、毎年5月に催される神泉苑祭がもっとも華やかです。
5月3日には「静御前の舞」も奉納されます。
また5月1日から4日まで行われる神泉苑狂言も圧巻です。
狂言堂で行われる古式ゆかしい狂言は、まさに日本古来の文化。
ぜひ、京ならではの雅な空気に触れてみてください。
参考文献
「冥き途 評伝 和泉式部」増田繁夫(1987年 世界思想社)
取材協力 : 神泉苑
〒604-8306 京都市中京区御池通神泉苑町東入る門前町166
電話番号 : (075)821-1466